
結局ほとんどの問題はお金の問題
先日は学部でのアメリカ留学はコスパ最悪という記事を書きました。
もちろんアメリカの学部での留学にもいい点はあるのですが、そのために支払わなければならない金額を考えると、コストパフォーマンスがとても悪いというのが私の考えです。
私は日本で学部を卒業した後、そのまま進学せずに企業に就職しました。

先日は学部でのアメリカ留学はコスパ最悪という記事を書きました。
もちろんアメリカの学部での留学にもいい点はあるのですが、そのために支払わなければならない金額を考えると、コストパフォーマンスがとても悪いというのが私の考えです。
私は日本で学部を卒業した後、そのまま進学せずに企業に就職しました。 続きを読む

東大の代わりにMITに通うことにすると、大学学部在学4年間で2000万円多くの費用がかかります。
この2000万円の差にまったく問題を感じないような裕福な方は、日本の大学でもアメリカの大学でも好きなところに行けばいいと思います。
しかし現実にはそのような恵まれた家庭はほとんど存在しないと思います。 続きを読む

この記事では『都会とはお互いが他人であるということが前提に人間関係が構築されている地域』と定義します。
高層ビルがたくさんあるとかは関係ありません。
その定義に合わせると、シリコンバレーを含むサンフランシスコベイエリアは、東京に比べて高層ビルやお店は少ないですが、様々な文化背景を持った人々が混在して仕事をしたり暮らしている街なので、都会だということになります。 続きを読む

なぜ日本でUberが普及しないかということが議論されているのをよく目にしますが、その原因は法律的なものや日本人のメンタリティよりも、Uberが東京や大阪など日本の都会に導入されてもそれほどインパクトがないというのが一番の要因のような気がします。
Uber登場以前のアメリカは行けないところばかりでした。
モータリゼーション以前に開発されたニューヨークやその他の大都市の一部は車がなくても生活できますが、そのようなところはアメリカのシティと呼ばれる場所でもほんの一部です。 続きを読む

理系を選択する人たちには、数学や科学好きだとか、子供の頃から電子工作やコンピュータを趣味としているといったイメージがあるのではないでしょうか?
過去の記事を読んでいただいた方にはわかるように、私は数学も科学も苦手で、科学や技術に興味のある家庭に育ったわけでもなく、大学3年生くらいまではどちらかというと政治や経済のような文系科目に興味のある人間でした。
私の学部の出身は慶応大学SFCというところで、そのころ話題になった分数ができない大学生がたくさんおり、私の当時の数学の知識も大学生としてはかなり残念なものだったと思います。 続きを読む

私がPh.Dを取得後、最初に勤めたのは大手ハードウェア企業でした。
その会社での私の肩書はソフトウェアエンジニアでしたが、ハードウェア企業なので当然会社の主役はハードウェアエンジニアです。
私の所属していたチームが開発するソフトウェアは、究極には似たようなものを社外から買ってくることが可能なものでした。 続きを読む

私は中学校の授業で初めて英語に触れました。
英語の教科書で一番最初にカバーされるトピックは、「How are you?」「 I am fine. Thank you.」といった会話で構成された文章ではないでしょうか?
私はアメリカに来るまで、この会話は練習用に作られた実際には使われない表現だと思っていました。 続きを読む

先日は情報収集という観点から英語学習で一番重視すべきはリーディングという記事を書きました。
英語を勉強するモチベーションは、日本語で手に入らない情報を手に入れるためだと思っているので、2番目に大事なのはリスニングです。
リスニングが重要だと思うのは、大学がオンラインコースを設置するなど、動画を通じて学ぶという方法が世の中で当たり前になってきたからです。 続きを読む

言語能力と一般に言った場合、読む(Reading)、聞く(Listening)、書く(Writing)、しゃべる(Speaking)の4つに分類されると思います。
ReadingとListeningは情報を手に入れるため、WritingとSpeakingは情報を発信するためです。
賢く生きていくために一番大事なのは、情報を手に入れることなので、英語の勉強は前二つ、特にReadingを重視していくべきだと私は考えています。 続きを読む
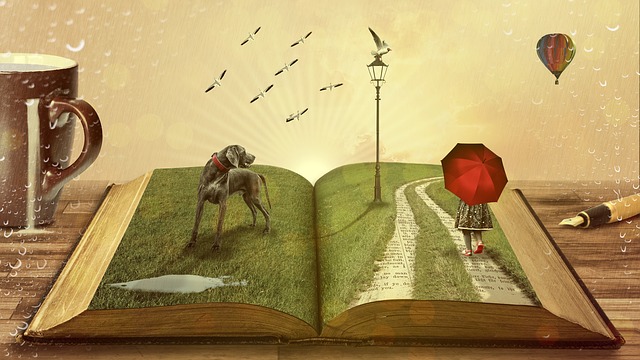
こんなやりとりがありました。
オープンソース全盛の現代においては説得力のないご意見です。
— yu. (@yu_phd) November 10, 2017
利用料を取る理論は使われないのでそのまま廃れます。似たような代替理論を出すことが難しくないことも多いです。
それを発明者が望むならばそれでいいですが、普通は社会で使われることで幸せを感じるのが研究者ではないでしょうか?無理だと思いません。
大半の数学者は公金がなくても、無償で理論を社会に提供し続けると思います。
なぜなら数学者の大半はお金が欲しくて数学をやっているのではなく、数学が好きだから数学をやっていると、私は思うからです。 続きを読む