
アメリカサラリーマン生活2年目・2013年冬
サラリーマン生活も2年目になりましたが、この頃が1番つまらなかった頃です。
会社の中を歩きながら『つまらなすぎてヤバい』と、窓の外のMount Hoodというきれいな山を眺めながら思っていました。
割り当てられる仕事は誰かが作ったものを修正したり、アップデートするというものばかりで、そういうものは確かに誰かがやらなくてはいけないことですが、一から新しいものを自分で作れるわけではなかったので完全に飽きていました。
結局一番の問題は、半導体製造技術に自分が興味がなかったことです。
これ以降の職場では、仕事を上司に割り当てられなくても、『自分がやりたいこと』や『チームのためにやった方がいいこと』がいくらでも見つかりました。
むしろ(あまりわかっていない)上司の仕事の指示が邪魔なので無視していたくらいです。
やっぱり仕事は好きなことをやるのが一番です。
やりたくない職場で一日我慢してもらった1万円と、好きな絵を描いてようやく手に入れた1万円。
同じ1万円でも充実感が全然違います。
夜型という遺伝子的に社会不適合な性質
会社は8時から17時までオフィスにいなければいけないことになっていたのですが、だんだん8時に行けなくなってきました。
家に帰ってからはDAWに夢中になっていたので、寝るのが遅くなっていました。
自分の場合は14時から24時みたいな勤務体系のほうが調子が出るので、上司に相談しましたがダメでした。
はじめて無職になった23歳になった時にわかったのですが、人間の体内時計は25時間サイクルというのは自分の場合本当で、何も制約がないと寝る時間と起きる時間が毎日1時間ずつずれていきます。
朝日を浴びると体内時計が24時間サイクルにリセットされると聞くたびにそれを試してみましたが、自分の場合はどうやら効かないようでした。
もちろん学生やサラリーマンであれば、朝決まった時間に行かなくてはならないので、無理をすればそれに合わせることはできますが、基本的に午前中から午後3時くらいまでは非常に調子が悪いです。
17時くらいから調子が出てきて、22時ころから深夜2時くらいまでが一番集中力が高まる気がします。
同僚に自分と似た人が一人いて、彼が言うには、自分たちは音に敏感すぎて昼間は作業に集中するにはうるさすぎ、周囲が静かになるから夜に集中力が高まるのではないかということでした。
なんとなく辻褄が合う気がします。
残念ながら社会は昼間に活動するように設計されています
変えられるものは変えたいと思いますが、体内時計が25時間サイクルだというのは努力でなんとかできるものだとは思えないので、受け入れるしかないと思います。
夜型の人は昼型に適合させようとすると体調が悪くなるので、夜型でもできる仕事を探して暮らすしかないと思います。
小学生のころは、野球と水泳とバスケットボールをやっていたのですが、野球が嫌いで、水泳とバスケは好きでした。
今振り返ると、野球は朝7時に練習開始だったのに対し、水泳とバスケの練習は夜だったというのがその原因かもしれません。
朝はとにかく子供の頃からダルかったです。
寝る時間は早かったので原因は睡眠不足ではないようです。
高校時代まで活躍していたのに、プロになってからは活躍できないスポーツ選手がたまにいますが、その理由はプロの試合は夜に行われることが多いため、朝型の選手が適応できないという話を聞いたことがあります。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
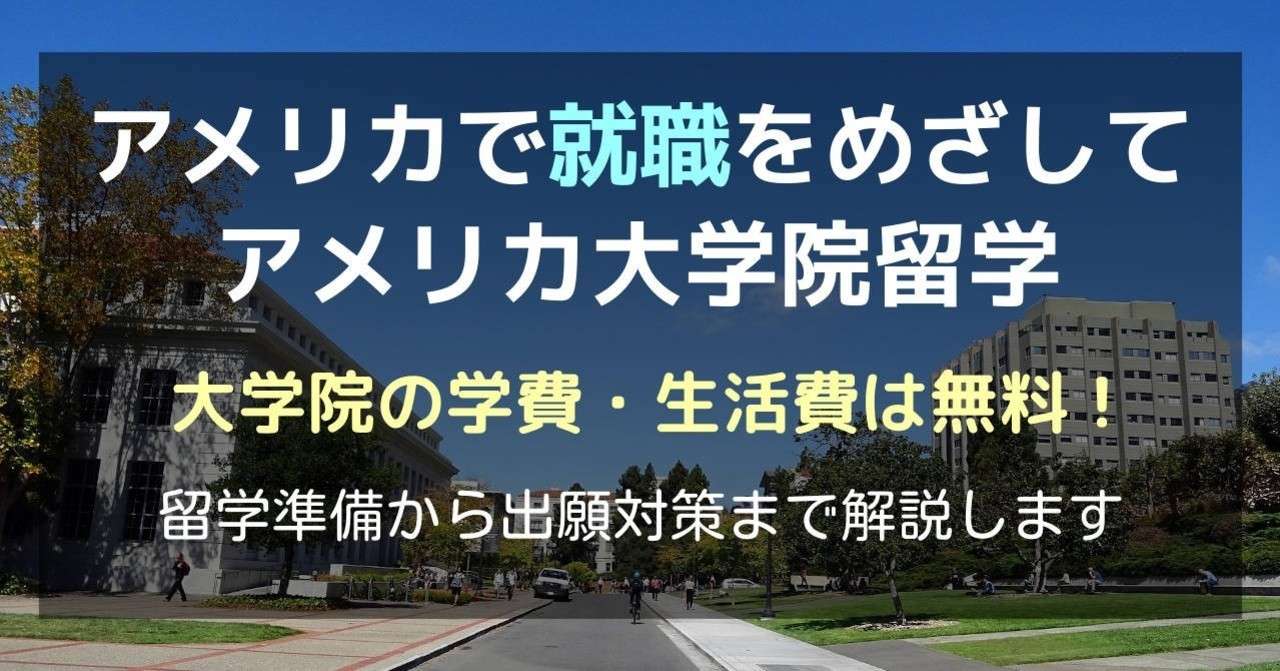


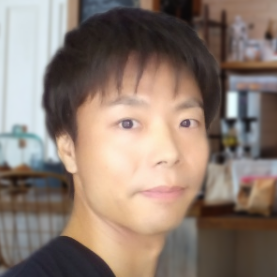 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。