
研究者を目指していない人が博士号をとる意味
医師免許や弁護士資格と異なり、博士号自体は国家資格でもなんでもないので、それ自体は研究者としての質を保証しません。
しかし研究者をはじめ博士号がないと就きにくい職業があるのは事実です。
少なくとも研究者になることが近い将来の目的ならば、大抵は取りに行くべきものでしょう。
私は24歳で大学院に進学しましたが、研究者を目指していない昔の自分と似たような境遇の24歳に、博士号を取りに行くべきかと聞かれたら正直答えに困ります。
人生は同時に2つの道を選べないので、アメリカに行く自分と行かない自分、博士号を取得する自分と取得しない自分を比べることができず、どちらがいいかは今でもわかりかねます。
アメリカ理系大学院在学中の反省点でも書いたように、博士号取得の一番のデメリットは20代の貴重な時間を多く取られることです。
私個人としては、博士課程での経験は仕事だけでなくそれ以外の部分でも生かされていると思いますが、それを得るために博士課程に行く必要があったのかどうかはわかりません。
博士課程で過ごした5年間の代わりに、企業に勤めていたり他のビジネスをやっていたとしても、似たような(もしくはそれ以上の)学びがあった可能性は大いにあります。
アカデミアの外の世界における博士号の価値
私が大学院に進学したのは、アメリカで就職するためのステップであり、修士でなく博士課程を選んだのは、大学院における学費免除や給与支給が博士課程の学生に対し優先的に与えられるというのが主な理由でした。
また博士号を持っていた方がアメリカにおいては就職しやすいのでは、という考え方を信じていたこともあります。
極端な話ですが、仮に日本社会が戦争などなんらかの理由によって壊滅的な被害を受けたとして、日本の外で生きていくことを余儀なくされるとします。その場合に博士号を持っていると、『ただの難民』ではなく『特別な難民』として扱われるのではないか、という打算的な考えもありました。(実際に自分が経験したことではないので真偽は全く不明ですが、例えば欧州では博士が尊敬されるという噂を聞いたことがあります。)
話を本題に戻しますと、日本だったら私は博士課程に進学をおすすめしません。
日本の企業において博士号取得者が優遇されるという話を、あまり聞いたことがないからです。
アメリカでは工学系に関する限り、博士号取得者に対してポジティブな印象はあってもネガティブな印象はないと思います。
私の実感では、機械工学では博士号を持っていることで就ける企業のポジションが多い気がします。
コンピュータサイエンスに関していうと、博士号がなくても修士号があればほとんどのポジションに応募できると思います。(博士号がないと応募ができない企業のポジションも多少はあります。)
またアメリカにおける労働ビザや永住権の取得という観点から見た場合、修士号取得以上の方は学部卒や高校卒の方と比べて優遇されますが、博士号取得者が修士号取得者と比べて優遇されるということは基本的にはないはずです。
また私が過去に勤めていたアメリカ大手メーカーでは、『学部卒+2年間の実務経験=修士取得相当』、『修士卒+3年間の実務経験=博士取得相当』という考え方があったと記憶しています。
実務における博士号取得者と非取得者の差
博士取得後、私が勤めたシリコンバレーにおける大手メーカーとスタートアップ共に、私の所属していたチームのメンバーの8割以上は博士号取得者で、残りが修士号取得者でした。
個人的な実感としては博士号取得者の方が優秀な印象があります。
ただそれは優秀な人が博士課程に進学する傾向があるだけで、博士課程に進学することで得られる何か特別な教育のおかげではないのかもしれません。
地頭的な部分では正直学歴はほとんど関係ないと思います。
1つだけ言える気がするのは、博士号を持っている人は過去の研究のサーベイが上手いという点です。
例えば業務上何らかの問題にぶつかった際に、博士号を持っていない方は自らそれを解決しに行こうとする傾向があるのですが、博士号取得者は過去の論文をあさり、出来るだけ過去のアプローチの組み合わせで問題を解こうとする印象があります。
そのような傾向がある理由は、とても忙しい博士課程大学院生活を通じて、時間を節約することの大切さを学び、また優秀な研究者を目の当たりにすることで、自分の無力さを思い知らされていることによる副産物なのではないかと私は想像しています。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
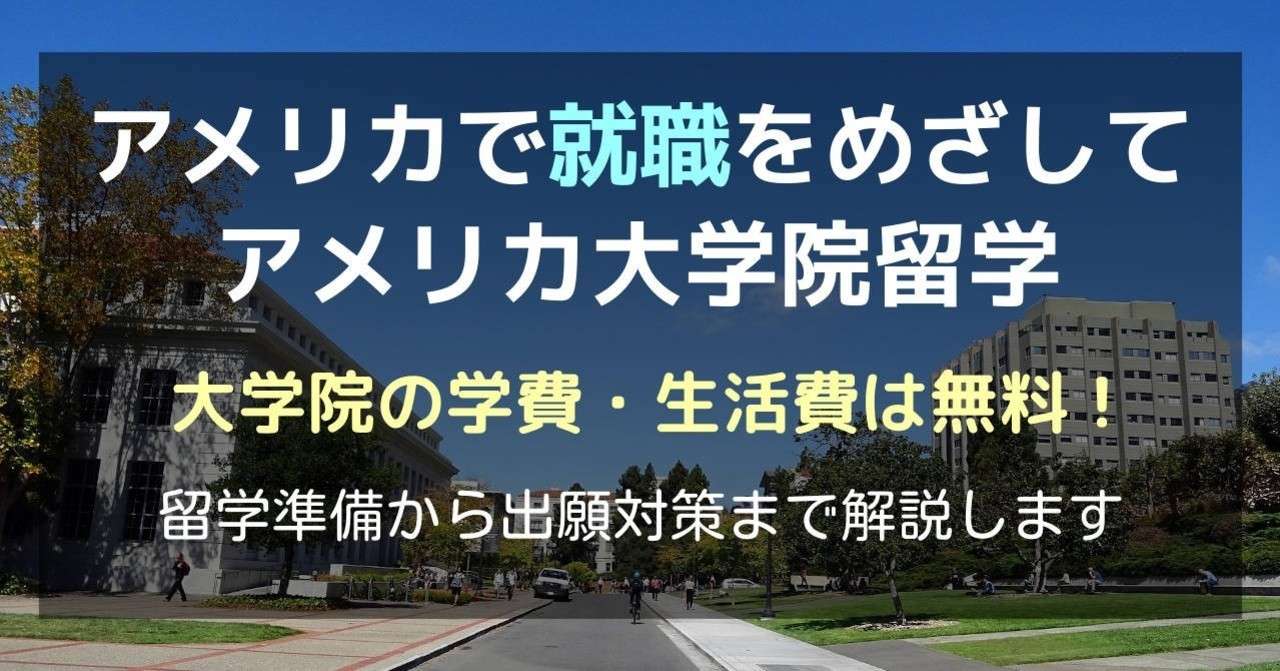


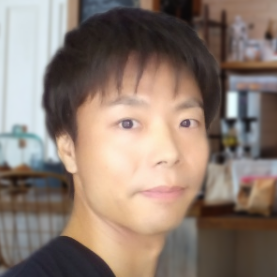 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。