
世の中のほとんどのことは判断できない
「医療デマ」対策に「リテラシーを身につけよう」は有効なのかという記事を興味深く読みました。
私は大学で始めてメディアリテラシーという言葉を聞きました。
メディアの提供する情報の真偽を自分で判断する力というようなニュアンスだと思うのですが、この記事の内容と同様に、最近は正直そんなことはほぼ不可能だと思うようになりました。
『子宮頸がんを防ぐためのワクチンが間違った情報によって普及が妨げられている』と主張している村中璃子さんという方がネイチャーに表彰されたというニュースがここ数日話題になっています。
こちらの村中璃子さんは同様の主張を長らく続けてきたようですが、ついに雑誌ネイチャーに表彰されることにより注目を浴びたようです。
ここで私が気になったのは、何か新しい知見が得られたから注目されたわけではなく、ただ単に『皆が権威があると信じている』雑誌が表彰したから注目されたという点です。
つまり彼女の主張がにわかに脚光を浴びた理由は政治的なものです。
逆に現在でもワクチンの副作用があると信じ村中璃子さんを批判している方もこちらの方のようにネット上にはたくさんいるようです。
まったく医学的な知見のない自分には正直どちらが正しいか見極めることはできません。
経済学のように現実世界で理論が成り立つことを検証することが難しい分野は仕方ありませんが、私は少なくとも理系にカテゴライズされる分野というのは、新しく提案された理論を必ずほかの人が再現できることを確定したうえで論文が掲載されると思っていました。
しかし不名誉なSTAP細胞の事件で私が一番衝撃を受けたのは、分野によっては内容の再現性を検証せずに、性善説で論文が掲載されるという事実でした。
そしてSTAP細胞の論文が掲載された雑誌も今回のワクチンの件と同じネイチャーです。
ネイチャーに表彰されたから主張が正しいに違いないという考え方は危険である気がします。
自分が経験したことだけは信じることができる
「ロボットは東大に入れるか」の新井紀子教授は研究者としてすごいという記事で、AIは写真のサイズやデジタル的なデータの変更があると使い物にならなくなるという主張に私は反論しました。
これは私のコンピュータビジョン分野のエンジニアとしての経験から、新井紀子教授の主張は正しくないと言う確信があるから書くことが出来ました。
東ロボプロジェクトでそれらが実際に問題になっていたならば、少なくとも私はエンジニアとしてそれを解決できる自信があります。
そして『AIは東大に合格できないことを証明する』という主張が、そんなに軽々しく言えるようなことではないのも、私の研究者・エンジニアとしての経験から言うことができます。
プログラマはコミュ障向きの職業
Demo or Dieの文化があるコンピュータサイエンスは、結果が政治力を上回る数少ない貴重なエリアなのかもしれない。
— yu. (@yu_phd) November 24, 2017
コミュ障はコンピュータサイエンスを勉強し、プログラマになるべきだという考えがよりいっそう強くなった。 https://t.co/9lk5dGUpOw
Twitterをやり始めて知ったのですが、研究不正というのは残念ながらよくあることのようです。
ネイチャーのような人々の信じる権威が政治的に使われることもよくあるのでしょう。
幸いにもコンピュータサイエンスは、人間のコントロール下にあるコンピュータの中での計算について扱う分野なので、新しいアイデアを提案したらそれがうまくいくことを目の前で実証することが多くの場合可能です。
MITのMedia Labの『Demo or Die』というモットーがそれを良く表しています。
動くものを実際に見せるのはなによりも説得力があります。
そこには政治的なかけ引きが入る余地はありません。
そしてコンピュータサイエンスをベースにしたエンジニアであるプログラマの世界では、手が動くことがすべてであり、口を動かすだけでモノを作れない人は誰も信用しません。
市場の力もコミュ障の助けになる
税金を原資とした国家予算の取り合いを見てもわかるように、政治の世界はゼロサムの世界です。
自分が何かを得るためには他の人から奪うしかありません。
逆に世界全体のGDPが毎年成長することからわかるように、経済活動はゼロサムではありません。
レストランで満足のいくおいしいものを食べ幸せになった人が、支払いの際にお金を奪われたとは考えないと思います。
レストランの側もサービスの提供の対価として、お金を手に入れることが出来て幸せです。
このように経済活動はWin-Winの取引です。
買い物やサービスの提供等の経済活動を通じて、政治的なかけ引きなど必要とせずに、人々はお互いを幸せにして日々の大半を過ごしているということは、あまりにも基本的なことのようで見落とされがちですが、とても大切なことだと私は思います。
勉強のできるコミュ障のあなたには、研究者の世界よりもビジネスの世界で生きることをおすすめする大きな理由がこれです。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
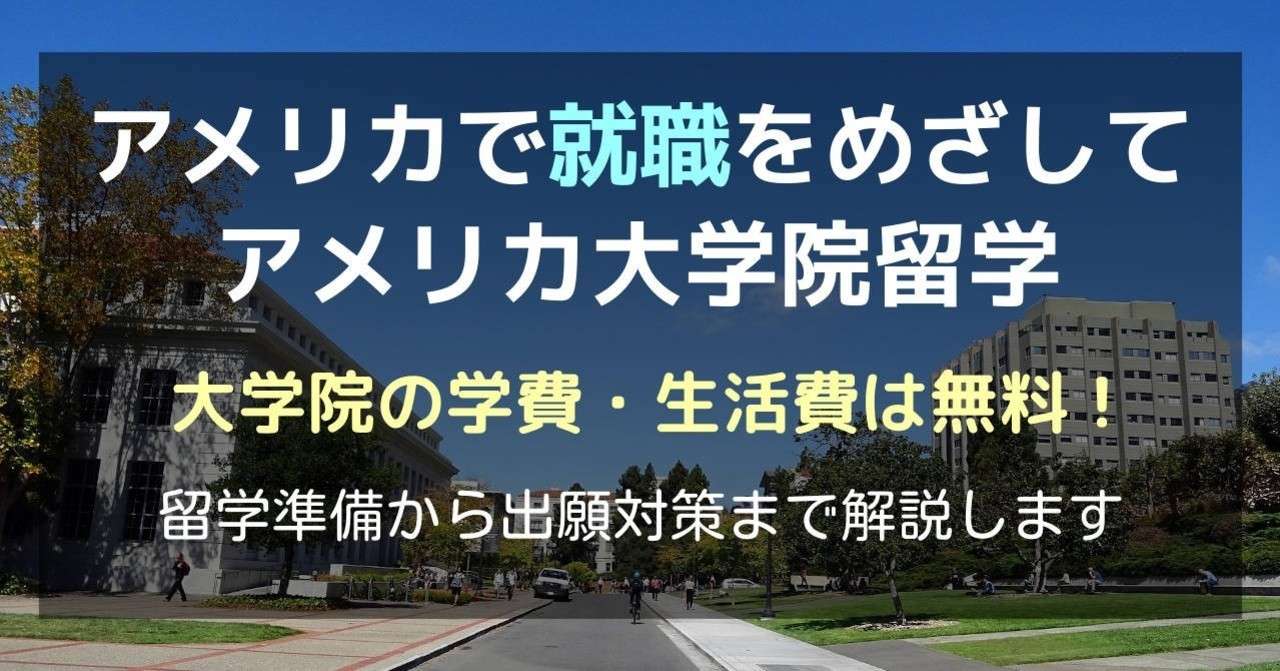


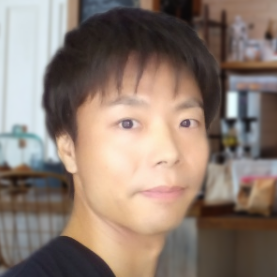 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。