
アメリカサラリーマン生活1年目・2012年春
シリコンバレーの大企業はとてものんびりしているという記事に書いたように、サラリーマン1年目はとてものんびりリラックスして過ごしていました。
大学院での研究は自分の仕事なので、自分がやらないと前に進みません。
会社での仕事は他の人の仕事を任されているだけなので、必要最低限だけやっていれば問題なしです。
もちろん会社の仕事も自分事と捉えることもできますが、自分がどんなアイデアを持っていようとも、結局組織というのは意思決定者が気に入らなければそのアイデアが採用されることはないので、自分はそのあたりを早々に諦めてしまいました。
逆に言えば、昇進して自分のポジションを上げることができれば、自分のやりたいことを実現するために他の人を会社のお金で使うことができるわけです。
つまりサラリーマンをやる一番のメリットは、自己実現のために自腹を切らずに組織を動かすことができることではないかと思います。
私のマネージャーはスタンフォードでPh.Dを取ったインド人の応用化学のエンジニアでしたが、就職してからはアメリカの新聞を読んだり、英語のアクセントを矯正したりして、昇進する努力をしているという話をしていました。
私はそのあたりに興味がなかったので、6年間のアメリカサラリーマン生活はずっと平ソフトウェアエンジニアのままでした。
私のいたチームは割と長く働いている人が多かったですが、10年近く働いている人が辞める時は大体エンジニアからマネージメントの方に移りたくなったというのが理由のようでした。
Intelはとても大きな会社なので、上が詰まっていて昇進が大変だからです。
天国のような日々だった
アメリカの博士課程の学生だったときは、これまで振り返ってきたように、貯金ゼロかつ日々大きなプレッシャーを感じる日々でした。
逆に会社では、マネージャーが常にオーバーワークにならないようにケアしてくれるなど、とても大事に扱ってくれます。
学生の時はお金を節約するために、お茶やコーヒーをタンブラーに入れて家から持って行っていましたが、会社では飲み物やフルーツが無料でした。
入社して最初の3か月間は勉強だけしていればよくて、チームの開発しているプログラムを適当に触ったりドキュメントを読んだりしているだけで毎月100万円が銀行に振り込まれるという状態に、とても不思議な感じがしたのを覚えています。
そのことを同僚に伝えると、どうせいずれ忙しくなるから大丈夫と言われました。
実際に夏以降はそれなりに割り当てられたプロジェクトをこなしていくことになるわけですが、目の前のお金を拾わなくてはならない小さなスタートアップと異なり、ゆっくりと時間をかけて開発することができたので、論文を読んだり勉強しながら仕事ができたのでとても贅沢な時間でした。
また会社ではプログラミング言語やデータ構造とアルゴリズム、データベース、チームでの開発の仕方、半導体製造技術など、様々な授業がときどき行われていて、そういうのはせっかくなので仕事が忙しい時も出るようにしていました。
チームで一つのものを作るという点が学生のときとの大きな違いで、gitのようなバージョン管理システムをはじめとしたツールや、コーディングスタイルを皆でそろえるなど共通の習慣を持つことが重要になってきますが、そういうのを知るという意味では余裕のある大企業にまずは就職するのは悪くないかもしれません。
大企業ではコンパイラやIDEも自動的に最新のものにアップデートされますが、スタートアップではそういう雑用も自分でやらなくてはならないのです。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
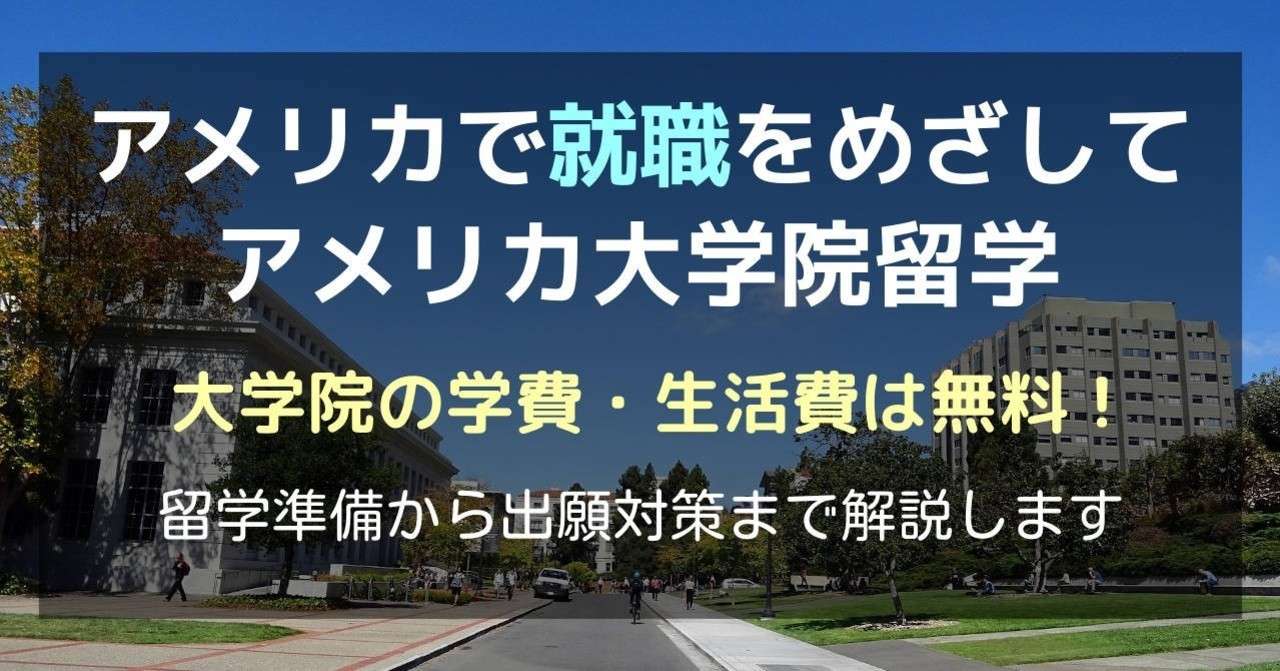


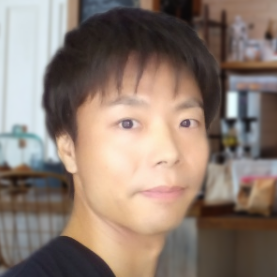 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。