
数学の勉強はとにかく進まない
最近仕事のために数学の論文を真面目に読む機会がありました。
私は面倒くさがりなので、論文や教科書を読んでいても、仕事に必要な部分だけを抜き出して、証明など知らなくても困らなさそうな部分は大抵スキップするのですが、今回は必要に駆られて全部を真面目に読む必要がありました。
数学の教科書や論文を真面目に読むと、1ページどころか1行進むのに数日かかったりします。
その1行を理解するために他の論文をゼロから読む必要があったりするからです。
そのような過程を久々に経験する中で、数学がまったく理解できなかったの頃を思い出しました。
以前文系少年がアメリカ理系大学院でPh.Dをとりシリコンバレーのプログラマになったきっかけという記事にも書いたように、20歳頃まで数学がさっぱりわかりませんでした。
私はどうやら大抵の人よりも記憶力がよいようで、英語の単語を覚えたり、歴史や地理の用語などを覚えることが小さいころから苦ではありませんでした。
それに対して数学や物理というのは、何かを覚えるのではなくコンセプトを理解する作業なので、記憶するだけではどうにもならないために苦手意識があったのだと思います。
数学や物理の教科書は一日一行しか進まなくてもそれでいい
一日に何百ページも読めるという速読という技術がありますが、それが可能かどうか以前に一日に何百ページも進んでしまうような本はかなり密度の薄い本と言えると思います。
数学や物理の教科書は、そのページ数が歴史や地理の教科書のそれと同じだったとしても、その密度がまったく異なります。
先ほども書きましたが、数学や数学で書かれた論文や教科書は一日頑張っても1行進まないことがあります。
でもそれは私だけでなく、数学が得意な人たちもおそらく同じはずです。
与えられた式Aが、次の行で式Bに変換されていたとしても、その変換ができる理由は必ずしも明確に書いてあるわけではありません。
その1行を理解するために、どんな知識が必要かを見出し、それを使って自分で行間を埋めていかなくてはなりません。
少し丁寧に書かれている論文だと、大学2年生くらいまでで習う数学がわかっていると読めるように書かれていたりします。それでも1行を理解するために、6歳から20歳までの10年以上の算数・数学の勉強の積み重ねが必要なわけです。
だからわからないときは、わかるところまで教科書をさかのぼるのも普通のことです。
私は高校で習うような数学の公式でもすぐに忘れてしまうので、いつもその都度検索して調べてます。
理系科目が本当に苦手かどうかは長期的に取り組まないとわからない
数学や物理などの理系科目に苦手意識のある人はたくさんいると思います。
一日頑張ってもまったく理解できずに、自分は理系に向いていないと思ってしまう方も多いと思います。
でも先ほど述べたように、それは別に変なことではありません。
わからないときは、その問題を頭の片隅にでもいれてしばらく忘れてください。
お風呂に入っているときなどに、ふと思い出して解決方法がひらめいたりします。
あなたが記憶力にすぐれているのならば、歴史や地理のような勉強は一通り本を読み流すだけでその内容を覚えてしまうかもしれません。
しかし数学は長い時間をかけながらほんの数ページを読み進めていくうちに、少しずつわかってくるものだと思います。
数学を理解するためには、何か月かかっても焦らずわかるまで我慢して大丈夫です。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
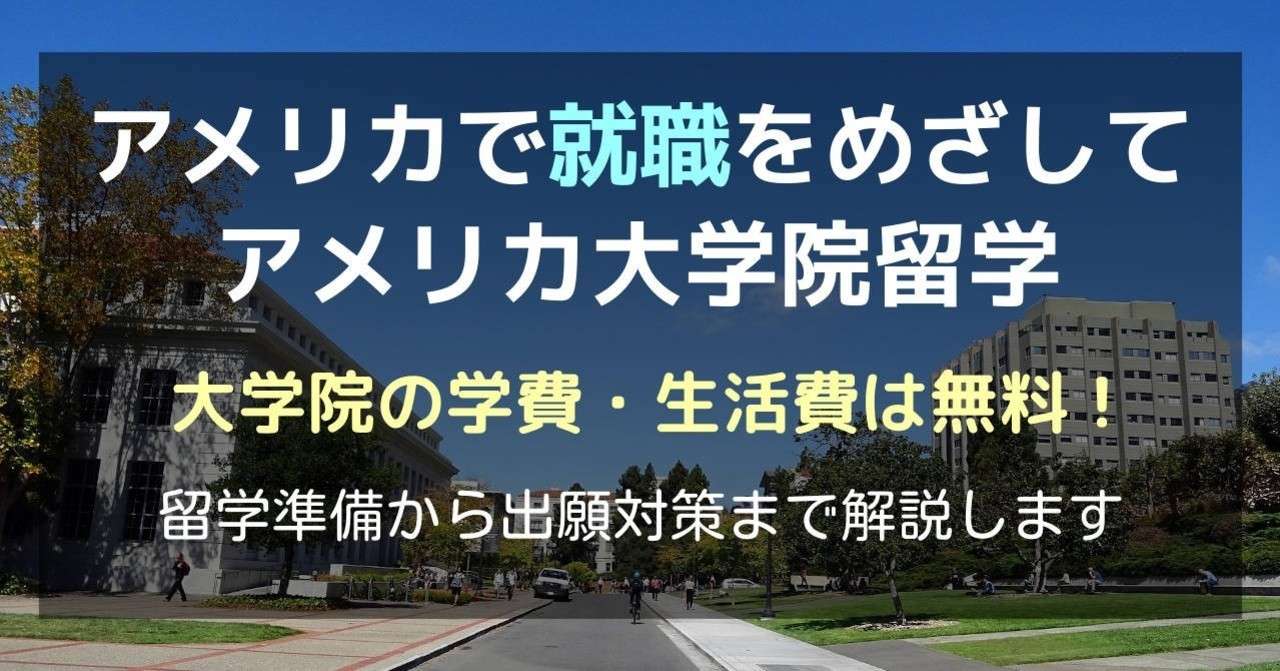


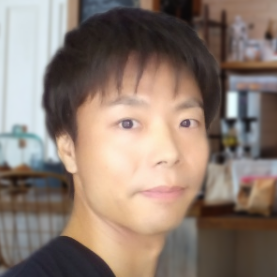 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。