
道を間違えたことに気づいたらその道を戻る
私はいまの現状にわりと満足していますが、ここまでくるのに15年近くかかりました。
もし今人生をやり直すとすれば、その半分くらいには時間を短縮できる気がします。
役に立ちそうだと思ってやってみたことが、やってみたら役に立ちそうもなくて時間を無駄にしたと思うことはいろいろとあります。
高校から大学に入ると、理系の授業に比べて文系の授業はとても魅力的に見えます。
電気や機械の話に比べて、歴史や国際情勢、経済などの話の方が実社会と密接に関連しているようで、聞いていてとてもおもしろく感じるのです。
しかしおもしろいけれど、自分の生きる力になりそうなものは何も残りませんでした。(文系少年がアメリカ理系大学院でPh.Dをとりシリコンバレーのプログラマになったきっかけ)
究極には文系の大学教授が話している内容は個人の感想だからです。
20歳で5年のビハインドを負う
せっかく情報系の大学に入ったのにもかかわらず、プログラマになるための勉強を本格的に始めたのは大学3年生の時で、この時点で私は大学の最初の2年間を無駄にしています。
高校で習う数学や英語もほぼ頭に入っていなかったので、他のまじめに勉強してきた人とくらべてその時点で5年遅れのスタートでした。
3年生の後半や4年生になって、1年生がとるべき微分積分や線形代数の授業を一緒に受けました。
実は大学の最初の2年間も一生懸命勉強しました。
もちろんその最初の2年間で学んだこともたくさんあるので、それを活かして何かやろうという考えもできたと思いますが、筋が悪いものを続けてもうまくいかないものです。
サラリーマンをやるのならば年収は業界によって最大値が決まりますし、ビジネスをやるのならばその対象のマーケット規模で最大の売上が決まります。
お客さんが少ないところでがんばってもどうにもなりません。
プロ野球チームは、すべて100万人以上の人口を抱える都市に本拠地を置いていることからも明らかです。
英語もちゃんと勉強していれば、こちらに書いたようにわざわざ会社をやめて1年間英語の勉強のために時間を割く必要もありませんでした。
専門分野も、コンピュータサイエンス→機械工学→コンピュータサイエンスと出戻りです。
機械工学を一度挟んだのは、もう少しハードウェアについて知りたいと思ったからなのですが、結局いまはソフトウェアの仕事に戻っています。
私の人生は回り道ばかりです。
時代によって、筋の良し悪しも変わってきます。
例えば2000年代前半では、日本のプログラマの待遇は本当にひどいものでしたが、Googleなどの外資ソフトウェア企業の日本オフィスが大きくなるにつれて、業界の金銭的な待遇がよくなってきました。
私はアメリカに行くことで高い給与をもらおうと15年前は考えていましたが、いまだったらとりあえずこの手の外資に入社することを目指してしまう方が筋がいいかもしれません。
埋没費用と機会費用を考えてゼロベースで行動する
私に対する質問で多く受けるものの一つに、文系だけど理系大学院に行けるかどうかというものがあります。
私の想像ですが、すでに一度大学を卒業しているのにもかかわらず、それをやり直すのは時間がもったいないと考えているからなのではないかと思います。
しかし既に過ぎてしまった時間は埋没費用なので、考慮に入れる必要は本来なく、今行くべきだと思う道を今行くべきです。
保有している株が値下がりしている状態で損失を確定する損切りは投資には不可欠です。
しかし損失を確定することの心理的な抵抗があり、人はその後株が上がることを期待して保有し続けてしまうものです。
しかしその株が上がらなければ、損切りをしてそのお金を他のことに使えたチャンスを失ったことになります。
つまり機会費用の損失です。
知り合いの経済学者に、『経済学ではなく工学をやっておけばよかった』と言われたことがあります。
『やりたければ今からやればいいのでは?』と提案したのですが、『せっかくここまでやってきたのもあるし。。』といわれました。
埋没費用も機会費用も経済学用語なので、彼はそのことを知っているのにもかかわらず、自分自身の人生にそれを適用するのは心理的なハードルがあるようです。
山で遭難したと考えればいい
山で遭難したことに気づいたとします。
そこからさらに前に進んで目的地へ向かう道に戻る方法を探しますか?
それとも来た道を戻りますか?
その判断です。
後者の判断の方が賢明ではないでしょうか?
前者は死の香りがします。
いつかうまくいくとわかっていてうまくいかない日々を耐えるのはありですが、頑張った結果として筋がわるそうだとわかったものは諦めて、次のステップに行ってしまうことがお勧めです。
結局今がうまくいけば、昔のことはどうでもよくなります。
私は『思い立ったが吉日』でやり直し派です。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
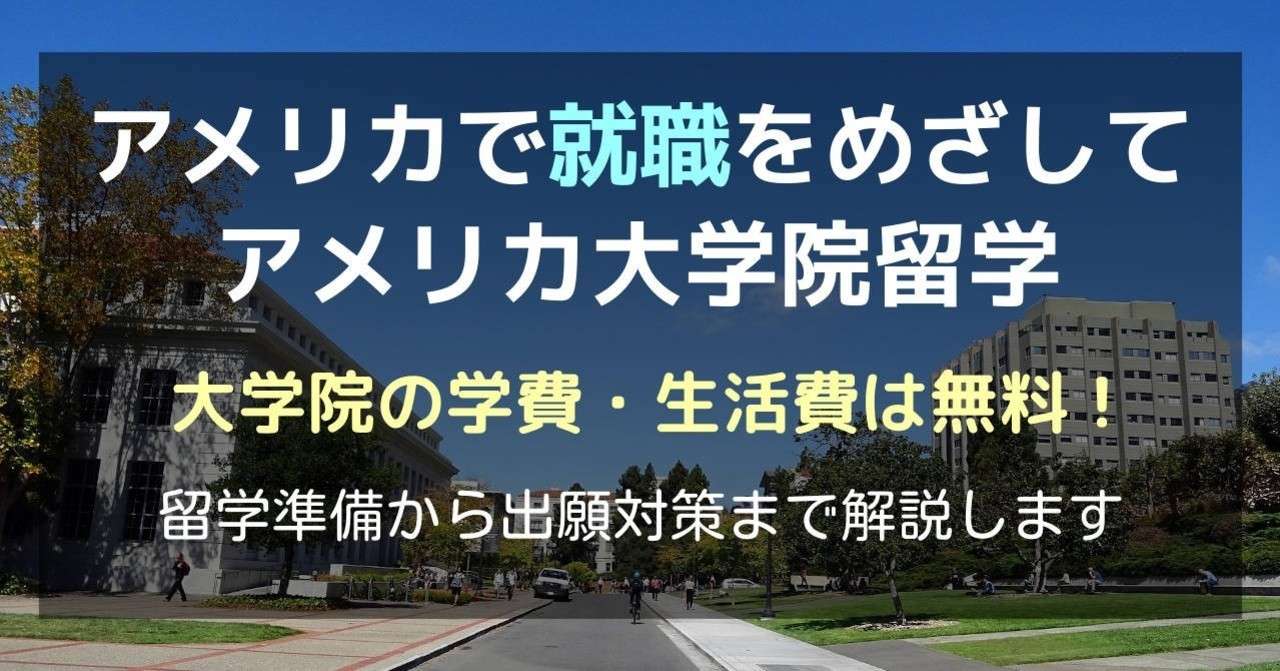


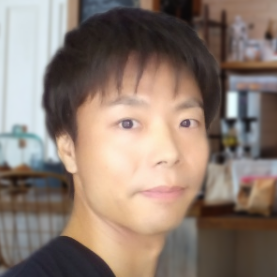 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。