
『学校で勉強しているだけでは大人になってから通用しない』という古臭い考え方
本当の教育格差とは、塾に通わせられる裕福な家庭と経済力がなく進学させられない家庭の格差ではなく、日本の学校で粛々と勉強させとけばいいと思い込んでる家庭と、それじゃあ今後は通用しない人材になってしまうと理解できてる家庭の格差。こっちのほうがよほど深刻。
— ちきりん (@InsideCHIKIRIN) January 1, 2018
『学校でおとなしく勉強しているだけでは大人になってからは通用しない』
この類の話は私が子供の頃からさんざん聞かされてきました。
つまりこちらのちきりんさんのツイート内容は全く真新しい知見でもなんでもなく、少なくとも20年前、下手したら30年前の昭和の匂いのする非常に古臭い価値観です。
そして私自身はこの考え方こそが、技術の核になる部分がハードウェアではなくソフトウェアに実装される時代に移行するにつれて、日本経済が競争力を落とし始めた要因の一つであると考えています。
ハードウェア開発では根性と行動力が物を言う
自動車や大規模構造物の設計のようなハードウェアの開発は、根本的にはソフトウェア開発に比べてとても難しいものです。
コンピュータの中で動くソフトウェアは完全に人間がコントロールできる世界の話であるのに対し、現実世界で使用されるハードウェアは不確実性が多く、理論だけで片付くところが多くはないからです。
コンピュータ内でのシミュレーション技術も過去に比べればかなり成熟してきましたが、現実世界での自動車の衝突実験はいまだに行われますし、橋や建物を建てる時も必ずsafety factor(安全率)を考慮し、理論値よりも大きな負荷がかかっても問題ないように設計されます。
これらの作業においてもある程度までは力学をベースにした理論がありますが、最終的にはひたすら実験をしてデータを取るという、試行錯誤と工夫の世界です。
現実世界における実験なので、ソフトウェアのそれに比べてコストも時間もかかります。
つまりハードワークが実る世界であり、知性も大事ですが根性と行動量もとても大事です。
ソフトウェア開発では純粋に知性が物を言う
プログラマ以外の人が、プログラマを観察していて一番働いているように見える姿は、コンピュータに向かってキーボードをたたき続けているときだと思います。
しかしプログラマの側からすれば、プログラミングの最中がもっとも頭を使っていない時間です。
プログラミングは自分の頭の中で既に確立している論理をコンピュータに伝えているだけだからです。
https://twitter.com/ochyai/status/612796067801776128
プログラマが本当に頭を使っているときはその論理を構築しているときですが、そのときはソファに寝っ転がっていたり、散歩をしているので、外から見たら生産的な活動をしているようには全く見えないでしょう。
ソフトウェア開発における生産の部分は100%頭の中で行われます。
そしてその思考を支えるのが勉強を通じて得た知識です。
知識の量こそが能力
ソフトウェア開発において、与えられる問題に対してその解き方は様々です。
問題を解決したとしても、いい解き方と悪い解き方があります。
解決方法の良し悪しは一般に実行速度とそれを実行するのに必要なメモリの量で評価されます。(参考:Big O notation)
与えられた問題に対して、理論的には実行速度が速い解決方法が知られているにもかかわらず、実行速度が遅い方法で解決するプログラマは悪いプログラマです。
実行速度が速い解決方法を提案できるプログラマは、それが出来なかったプログラマよりも頭の回転が速いわけではありません。
多くの場合は前者が後者に比べて単純に多くの知識を持っていることが要因です。
「日本の教育は世界標準とずれている。黙って下を向いて、ひたすらノートを取っているなんてあり得ない」。幼少期を海外で過ごした日野田さんは帰国後、大学の授業に衝撃を受けた。「これでは高校の延長。知識の詰め込みではなく、論理的思考法を学ばないと世界で戦える人材は育たない」
(出典:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO25247470Z21C17A2M12000/)
従ってこちらの日野田さんのアイデアと私の考え方は真逆です。
結局人の強みはどれだけの知識を持っているかだと思います。
そして日野田さんにとって都合の悪い事実かもしれませんが、アメリカの工学系における大学、特に大学院教育は極端な詰め込み教育です。(音楽を専攻していた方も同じことを言っていました。)
これは知識があることが能力だという認識があるからだと私は考えています。
ディスカッションをすることで自分の持つアイデアがよりよくなったりすることはありますが、能力そのものが磨かれることはないと思います。
仕事をしている中で知識不足を感じた場合、『それでは誰かとディスカッションをしよう』となるでしょうか?
大抵の人はそれに関する書籍を購入したりして自分で勉強をするはずです。
アメリカのソフトウェア産業を支えているのは、インドや中国をはじめとする主に途上国の学校で詰め込み教育を受けてきた人間です。
そして彼、彼女の多くは博士号を持ち、その強みは学校で身に着けた知識とそれを発揮する知性だという認識がもっと広まるといいと思います。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
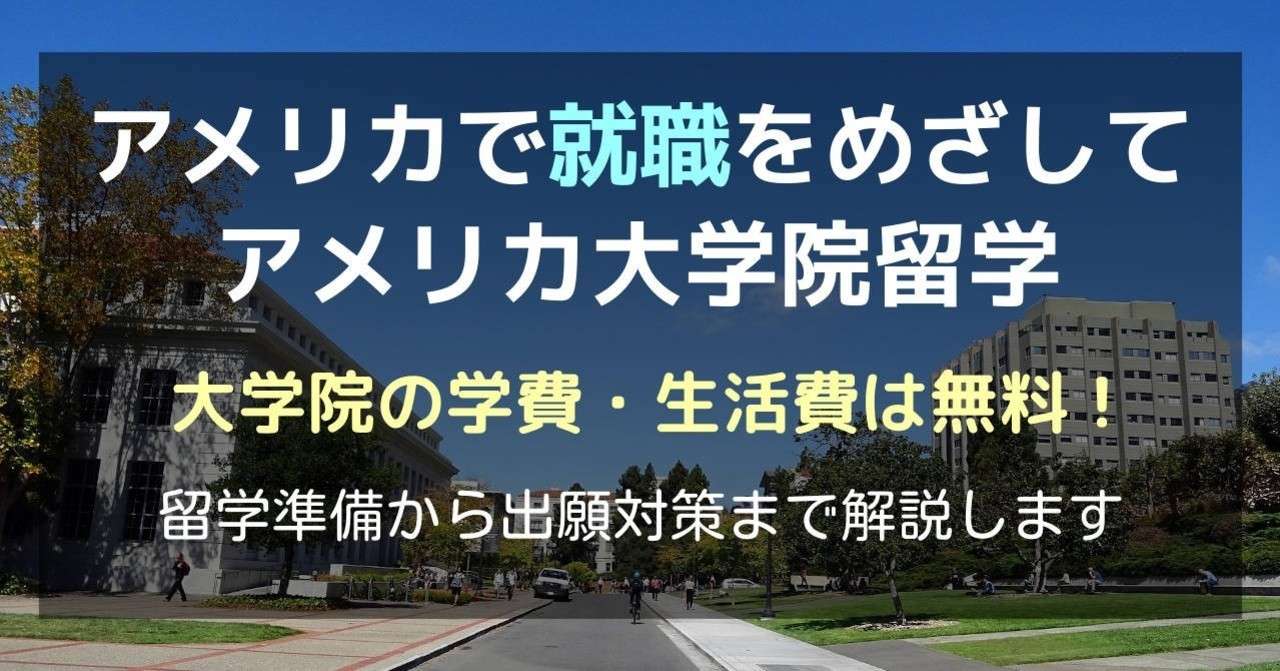


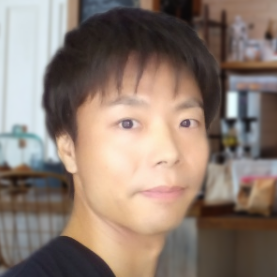 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。