
アメリカサラリーマン生活5年目・2016年冬
ついにサラリーマン生活も5年目に入ってしまいました。
仕事自体はこの頃とてもいい感じでしたが、サラリーマンを3年で辞めて好きなことをやろうときめていたので、さすがにそろそろ辞めなくてはいけないと考えはじめていました。
去年の夏から新規にはじまったVRのプロジェクトはプロトタイプができてきて、商品化にはまだ遠いながらも、とりあえずやっていることは間違っていなさそうな感じであることは見えてきました。
前回の記事に書いたように、このとき会社では2つのプロジェクトが同時に走っていて、もう一つのライトフィールドビデオカメラのほうがメインで、私のやっていたVRの方はどちらかというとサブのような感じでした。
しかしプロトタイプができてから会社のほうが本腰を入れ始め、マーケティングの人やらプロジェクト管理の人やらが入ってきて、プロジェクトに参加する人も 少しずつ増えてきました。
そして会社のギアを入れ替える目的なのか、年末に技術系のトップであるハードウェアとソフトウェアそれぞれのVPがレイオフされ、新たな技術VPが社外からやってきました。
この新たなVPがモンスターでした。
大きな組織変更があり、プロジェクトの方向性が自分の知らないところで決まるようになってきました。
私だけでなくCTOですら関知していなかった技術的な決定も多々あったので、今振り返ってもおかしなことになっていたと思います。
エンジニアだけのミーティングの際に、 CTOは『ビジネスサイドの人間が何を言おうが、それを聞かずにエンジニアはこれまでみたいに自分たちがやるべきだと思うことをやっていけばいい』と言っていたのを覚えています。
自分も同じ考えでしたが、私の新たな直属のマネージャーはモンスターVPの流れで行くように私に伝えてくるので、政治的にかなり難しい状況でした。
私は当時カメラのCalibrationという部分を担当していました。
空間の光をレンズがどのように写真として投影されるかを記述する数学モデルがあるのですが、実際のレンズは同一メーカー同一モデルのものでも様々で、必ず数学モデルとの間に誤差があり、その誤差を補正するのがCalibrationの作業です。
あるときどこか知らないところでCalibrationが議題にあがったようで、光学担当の同僚が新たなCalibrationの提案を全体メールでしてきました。
しかしそれは私の使っていた数学モデルと違うモデルを前提とした提案でした。
それを指摘するや否や、突然私のマネージャーが飛んできて私がどの論文の数学モデルを参照しているのか聞いてきました。
そのあと何があったのかはわかりませんが、その光学担当の同僚は次の日に会社を去ることになりました。
そもそもCalibrationを担当しているのが私だけなのに、それが私のいないところで議題になるのが不思議な話です。
そしてその光学担当の同僚も犠牲者のような気がします。
なぜなら彼は私が参照している論文とは異なる論文を『誰かに紹介された』のが事の発端のような気がするからです。
担当しているのは私だけなのに、彼にそれについて直接聞かれたことはなかったので、誰かが正しくない情報を彼に伝えているはずです。
いい雰囲気だったプロジェクトは嫌な感じになってきました。
Blenderをはじめた
投資の勉強はキリがないので、とりあえず終わりにしてこの頃から実践で投資を始めてみました。
最初はなくなっても困らない額から少しずつ始めていく感じです。
投資の勉強を終えたので、音楽づくりを再開してもよかったのですが、パートナーの提案でアートとしてのCGをプライベートで始めることにしました。
Blenderというのは昔からある有名な無料のCGソフトウェアなのですが、この数年前からグローバルイルミネーションをはじめとして当時は高価なソフトウェアにしか実装されていなかったような機能が使えるようになっていて驚きました。
最近では有名なアニメプロダクションもBlenderに乗り換えているようで、 プロが使っているものと同じクオリティのものが無料で使えるというオープンソースの流れは加速するばかりです。
本当にすばらしい時代がやってきたと思います。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
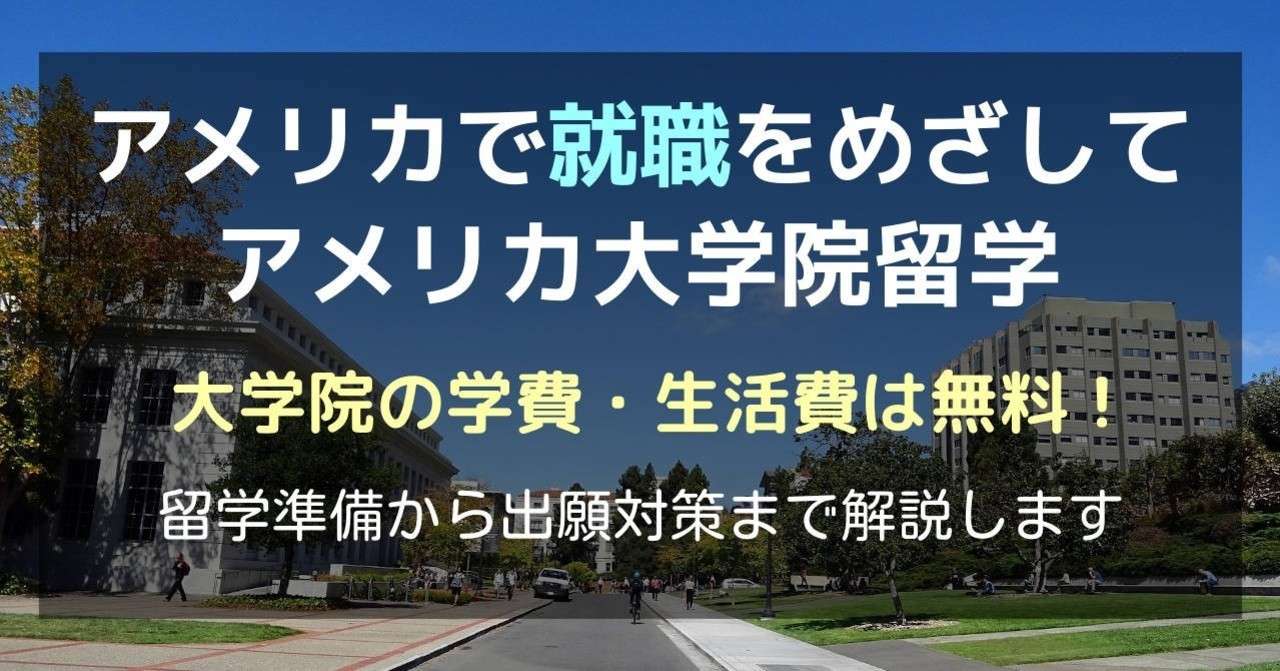


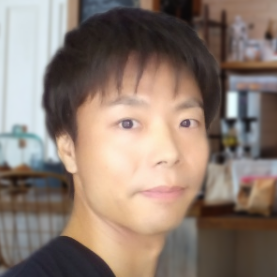 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。