
アメリカサラリーマン生活3年目・2014年春
ポートランドでの3回目の春を迎えました。
当時の写真を見返しても季節感のあるいいところだったと思います。
前回も書いたように、Intelでの2年8か月はリラックスした生活でいい思い出がたくさん残っています。
その理由の大きな部分は職場の環境がとてもよかったことだと思います。
あそこまで成功するような企業のカルチャーのおかげかマネージャーの環境づくりが優れているのか、チームの雰囲気はとてもよく、一人でいることを好む自分のような人間でも離れるのが少し寂しかったです。
マネージャーがインド人で、インド人主体のチームというのもよかったのかもしれません。
彼らはとても家族的です。
仕事とは別にチームビルディングイベントというのもよくやっていて、単純に近所にみんなでお酒を飲みに行ったり公園に行ってバーベキューをしたりするだけでなく、ボランティアをすることもありました。
その中でも面白かったボランティアは、国立公園のハイキング道づくりと低所得者向けの家作りです。
電気や水回りの配線などはプロに任せるのですが、その他の作業はコストを下げるためにボランティアで家を建てるそうです。
材料は工場で既に切り出してあるものなのでそんなに難しくありません。
言われたとおりに材木を釘で打ち付けていくだけです。
おじさんが大工さんだったので子供のころは横でよく作業を見ていたのですが、昔の大工さんは材料を切り出すところから始めるので職人感がありました。
今の大工さんは切るという作業がほとんどなさそうです。
素人が建てた家に住みたいか?と上司が冗談ぽく言っていたのを覚えていますが、アメリカでは新築住宅でも床が斜めだったりドアがはまらなかったりするのはよくあることなので、割と家というのはなんとなく建ってしまっているのかもしれません。
家だけでなく、例えばバスの自動ドアの閉まり方ひとつとっても、日本のものはとても繊細にできていると思います。
アメリカのバスの自動ドアの閉まり方やトラックの荷台の動きはとても武骨です。
『とりあえず動けばいいだろう』という強い意志を感じます。
住宅や自動車をはじめ、ハードウェアはモノの出来の良さがその商品の寿命につながったりするので、繊細にモノをつくるというのは大切なことです。
しかしソフトウェアには摩耗などによる物理的な寿命がないので、そういう細部にこだわる繊細さよりも 『とりあえず動けばいいだろう』 でモノを作るスピード感の方が大事なのが難しいところです。
転職活動
上司にカリフォルニアに引っ越すことにしたと伝えたのは3月で、実際の転職は8月だったので、転職活動には5か月ほどかかりました。
この時失敗だったのは、複数の企業への応募を同時にしなかったことです。
現在応募しているところから不採用の通知が来るまで次の企業の応募を始めなかったので、必要以上に時間がかかりました。
一度転職を決めたならば複数の企業の採用プロセスを同時に進めることが大事です。
最初はなんとなく同時に進めるのは失礼なのかなと考えてしまったのですが、向こうもこちらの事情などお構いなしに数週間連絡が途絶えた挙句に不採用を通知してくるので、そのあたりはドライに進めるべきだと思います。
現実問題として複数の採用プロセスを同時に進めるほうがよく、その理由はもし二つ以上の会社から採用の通知をもらえた場合はそれを材料に給料の交渉ができるからです。
このときは事実上初の転職で、そういうことは知らずにわりとナイーブに言われたままのオファーを受けてしまいました。
給料の差は、能力の差よりも採用時の交渉力でかなり決定される部分があります。
そして大抵その差は同一企業に勤めている場合の昇給よりも大きいので、アメリカ西海岸のソフトウェアエンジニアはみな頻繁に転職してしまうのだと思います。
シリコンバレーのソフトウェアエンジニアの平均勤続年数は1年半だそうです。
長く同じところで働いている人は会社の歴史を知っている分頼れる人が多いので、会社側がなぜ昇給をあまりしたがらないのかわかりません。
将来会社経営をすることがあれば、そういうこともわかってくるかもしれません。
↑記事をシェアしてください!読んでいただきありがとうございました。
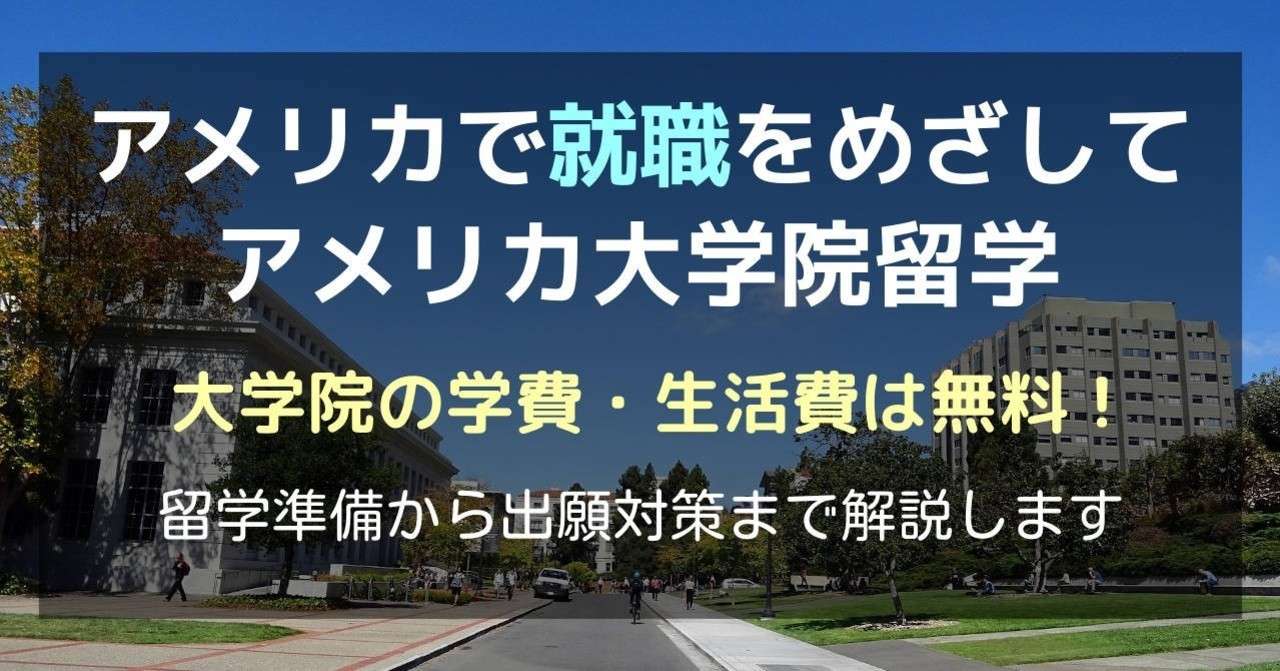


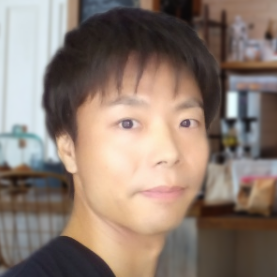 慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。
慶応大学環境情報学部を首席で卒業。日本のベンチャー企業で働いたのち、アメリカにわたり、カリフォルニア大学バークレー校にて博士号を取得。専攻は機械工学、副専攻はコンピュータサイエンス。卒業後はシリコンバレーの大企業やスタートアップでプログラマとして働いていました。現在はフリーランス。毎日好きなものを作って暮らしてます。